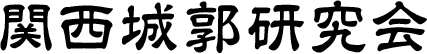12月の例会は、置塩城(兵庫県姫路市)を訪れました。
参加者は、会員に加え、お城のボランティアガイドをされている方々を含めて総勢36人でした。
現地の説明は、姫路市教育委員会の学芸員であり、姫路市埋蔵文化財センター所属の河本さんにお願いしました。
当日は、天気は良かったのですが、非常に寒く感じる日でした。
姫路駅で集合し、バスに乗車し、バス停から、置塩地区を歩いて、登山口に向かいます。
遠くの高台に、赤松氏の集落跡が見えます。

勇壮な置塩城が近づいてきました。
眺めるだけで、赤松氏の大城郭だということが分かります。

登城前に、全員集合です。
今回の担当者は、関西城郭研究会の会長でもある森さんです。
しっかり、諸注意を聞いて、安全に山城を攻略しましょう。

いよいよ、登城開始です。
置塩城は、麓から280mの高さにあります。
足元に気を付けて、ステッキを利用しながら、登っていきます。

大人数なので、前後に長い列となって、一歩一歩登っていきます。
50分くらいかかったでしょうか。

途中、道程を示す指標があります。
「今、〇〇丁目!!~」と、みんなで声をかけあって登りました。

お城の入口で、学芸員さんと合流しました。
まず、縄張り図をもとに、置塩城の全体のことや、石垣の残っている部分の説明を聞きました。

突然現れる、石垣です。
これは、Ⅱ郭周辺の石垣です。
こんな、山の上なのに、結構しっかりした石垣が残っていることに驚きです。

Ⅰ郭とⅣ郭の間の石垣です。
置塩城でも、よく紹介される石垣です。
ここでも、多くの質問が寄せられました。
特に、姫路城のとの一門との関係は、みんな食い入るように聞いていました。

巨大な自然石が組み込まれている石垣です。
巨石の大きさに圧倒されます。

本丸周辺の土留めの石垣です。
この形式の石垣は、いたるところに見られました。

ついに本丸に到着です。
「置塩城は、赤松氏のプライドをかけた大城郭です」という学芸員さんの言葉が、身に染みて分かります。

発掘調査の跡の説明です。
せん列建物の跡が出てきた場所です。
当時の人々の生活の様子が、垣間見れます。

一つ一つ、曲輪ごとに、丁寧に説明をしてもらいました。

ふと見ると、きれいな虹が!!!
山城の上から、虹を見下ろすのは、格別です。

本丸からの眺めです。
遠く姫路の町が見えます。
その向こうには瀬戸内海がキラキラ光っています。

さあ、午後の部の開始です。
まずは、Ⅳ郭からです。
しっかり、土塁が残っています。

Ⅲ郭に来ました。
置塩城は、山の上に多くの曲輪があり、そこに多くの居館があったことが伺えます。

足もとを見ると、きれいに石垣が並べてありました。
当時は、築地塀があったと推定できます。
説明がないと、知らずに通り過ごしてしまうかもしれない箇所です。

Ⅱ郭の庭園跡の立石です。
当時から、この石は立ったままです。
城主もこの石を、見ていたのですね。

Ⅱ郭の周辺には、塀が建っていたであろう石垣がありました。

Ⅵ郭から見上げる切岸です。
縄張り図で見るより、実際に見上げると、そのすごさが実感できます。
置塩城は、高い切岸が、防御の中心となってたのですね。

Ⅵ郭から眺める城下です。
当時は、この方向に城下町があり、見せるための石垣はこちら側に多くあります。

Ⅵ郭の下には、大石垣がありますが、危険なため、下りて見学するのは断念しました。

置塩城の見学は、ここまでです。
学芸員の河本さん、丁寧な説明ありがとうございました。
担当の森さん、大人数のお世話、ありがとうございました。
実際に登ってみて、赤松氏の居城である置塩城のことが、とてもよく分かりました。
参加された方々、お疲れ様でした。

ブログを読んでくだっさった会員以外の方、お城が好きな方、興味ある方、ぜひ一度お城を巡りましょう。
ホームページにあるお問い合わせフォームにお気軽にご連絡ください。
写真 西mura 文 田naka